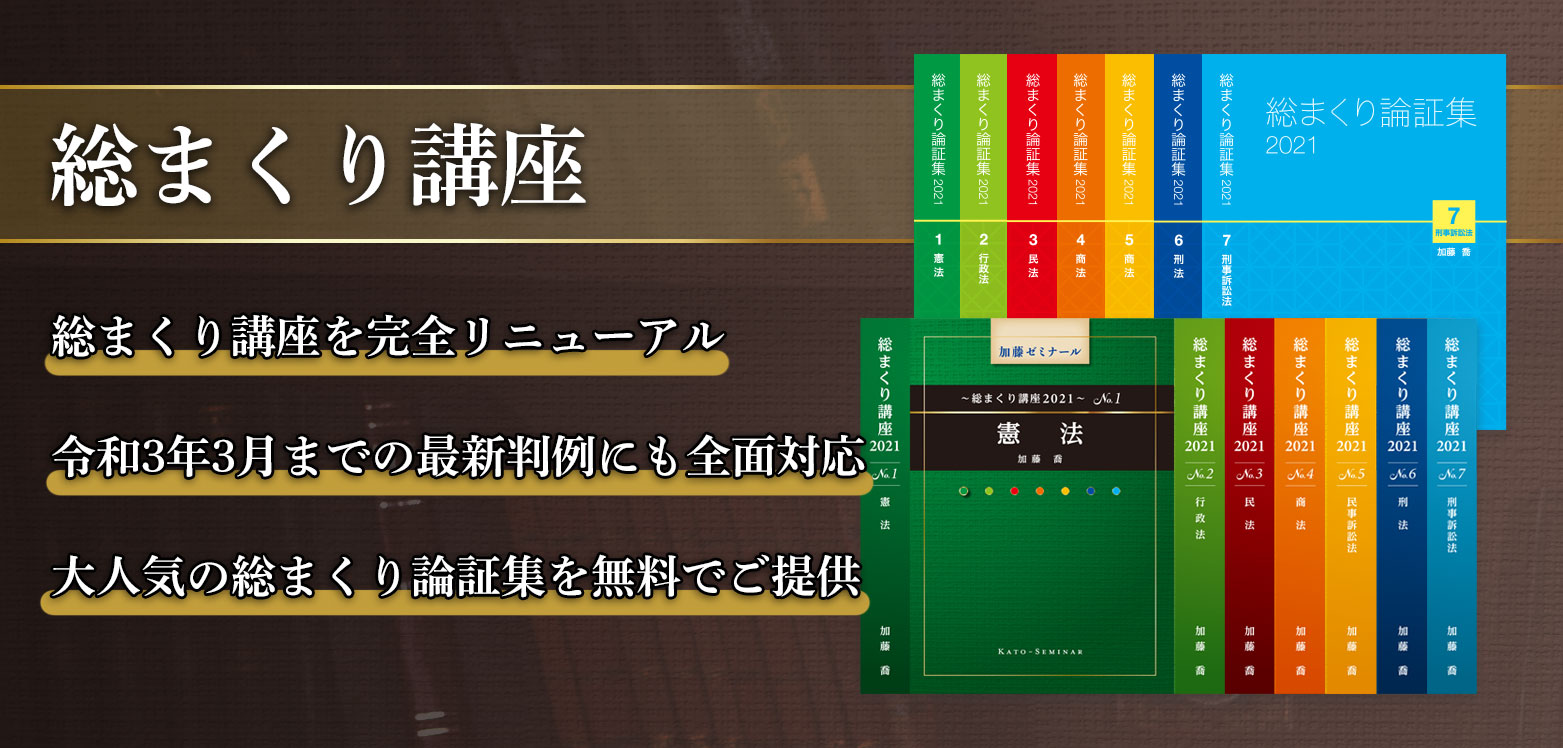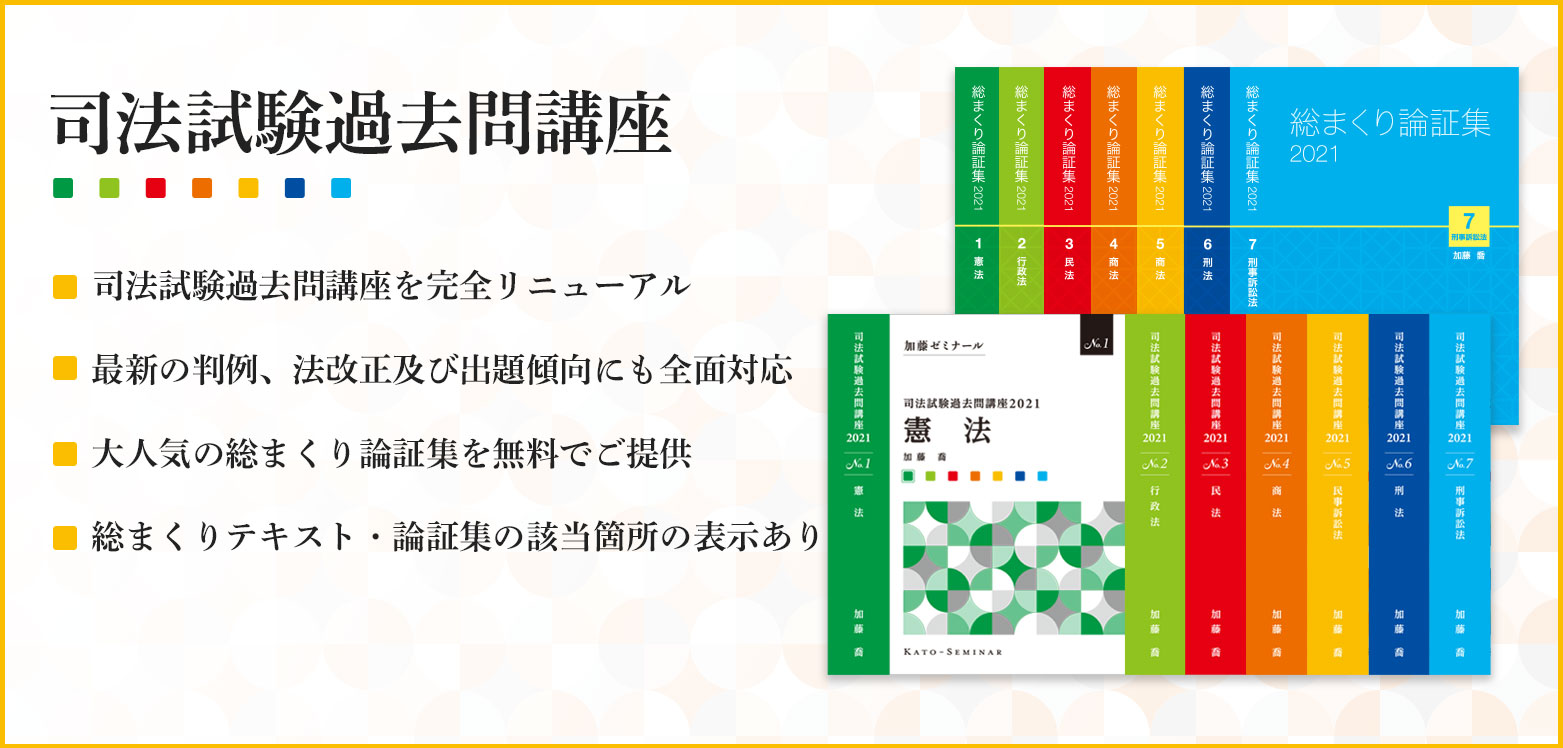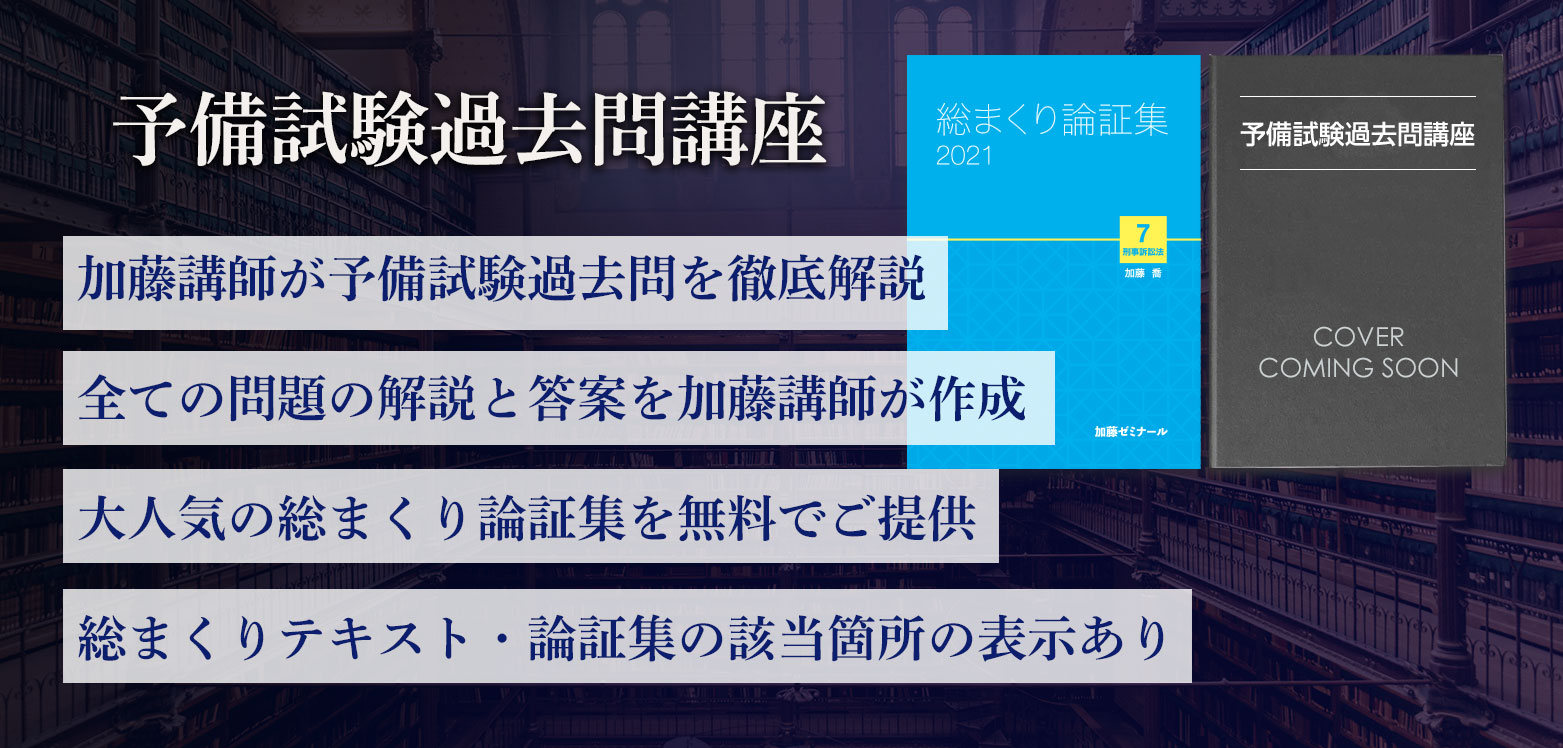令和2年予備試験論文試験で出題された論証のうち、どれだけ総まくり論証集に掲載されているのかについてご質問を頂きましたので、科目ごとに説明いたします。
結論から申し上げますと、令和2年予備試験論文と総まくり論証集は、全科目において、ほぼ100%対応しています。
.
憲法
犯罪被害者及びその家族等のプライバシーを保護するために「報道関係者」が「犯罪等」について「犯罪被害者等」に「取材等」をすることを事後的段階的規制(中止命令⇒罰則)により制限する立法の合憲性が問われた事案において、①取材の自由の憲法上の保障、②明確性の原則(憲法31条、21条1項)、③取材規制の憲法21条1項適合性(実質的観点)の判断枠組みが問われており、③では④事後的かつ段階的規制の評価も問題になります。
①~④は全て、総まくり論証集でA~Bランクの事項として掲載しています。
① Aランク(論証あり)
② Aランク(論証あり)
③ B論証あり(博多駅事件決定の比較衡量の枠組み)
⇒目的手段審査はAランク
④ Aランク
.
行政法
設問1では、①公害防止協定の法的拘束力が問われています。
① C(論証あり)
設問2では、都市計画法上の開発不許可処分の事前手続として自主条例により定められている事前協議に応じない旨の本件通知(法令上明文で定められていない)の処分性が問題になっており、法令の合理的解釈により法令上の根拠を認めることの可否(労災援護費不支給決定に関する最高裁平成17年判決等)、②前倒し的な法的効果の読みにより直接具体的な法的効果を認めることの可否(土地区画整理事業計画決定の処分性に関する大法廷平成20年判決)、及び③権利救済の必要性から例外的に処分性を認めることの可否(病院開設中止勧告に関する最高裁平成17年判決)が問われています。なお、④開発許可に係る公共施設管理者の同意拒否に関する最高裁平成7年判決の射程を論じる余地もあります。
① Aランク(判例を踏まえた答案例あり)
② Aランク(論証あり)
③ Aランク(判例を踏まえた答案例あり)
④ Aランク(判例を踏まえた答案例あり)
.
民法
設問1では、B(Aの娘)が意識不明のAの入院費用を捻出するためにAを無権代理してCとの間で100万円の金銭消費貸借契約を締結し、Cから受け取った100万円をAの入院費用の支払いに充てた後、自ら家庭裁判所に申立てをすることによりAの成年後見人に就任したという事案において、①無権代理行為に関与した後見人による追認拒絶の可否、②事務管理者が本人名義でした法律行為の効果帰属が問われています(②まで問われているのかは、定かでありません)。
① Bランク(論証あり、本件の同種事案に属する判例の事案の掲載もあり)
② Bランク(論証あり)
設問2では、本件不動産以外にめぼしい財産を有しないAがEから騙されて3000万円相当の価値を有する本件不動産を300万円でEに売却し、Eへの所有権移転登記もなされたという事案において、債権者Dによる③債権者代位権(強迫取消権の代位行使+原状回復請求権の代行行使)及び④詐害行為取消権の行使が問われており、③では強迫取消権の行使上の一身専属性、④では詐害行為該当性と受益者Eの悪意が論点になります。
③ 債権者代位権はAランク分野である上、行使上の一身専属性の判断枠組みについても掲載あり(但し、取消権固有のことは、総まくりテキストにのみ掲載あり)
④ 詐害行為取消権はランク分野である上、424条の2~4の特例に該当しない場合における詐害行為性の判断枠組みも掲載あり
.
商法
設問1では、甲社の完全子会社である乙社の取締役Bが、甲社の取締役A(甲社株式の40%を保有)の提案に従い、市場価格150万円の本件ワインを300万円で乙社に買い取らせたという事案において、Cが甲社の株主として①Bの乙社に対する損害賠償責任及び②Aの甲社に対する損害賠償責任を追及することの可否が問われています。
①では、㋐多重代表訴訟、㋑直接取引の成否、㋒直接取引を理由とする任務懈怠の推定(公正な取引条件説)、㋓任務懈怠推定を覆すことの可否、及び㋔免責事由の証明による免責の可否が問われています。
㋐ Bランク(条文及びその説明あり)
㋑ Aランク
㋒ Aランク(条文及び公正な取引条件説の論証あり)
㋓ Aランク(公正な取引条件説からの説明あり)
㋔ Aランク(条文の掲載あり)
②では、㋕株主代表訴訟、㋖親会社取締役の子会社に対する監視監督義務、及び㋗子会社損害と親会社損害の関係が問われています。
㋕ Bランク(条文及びその説明あり)
㋖ Aランク(論証あり)
㋗ Aランク(論証の理由付けとして掲載あり)
設問2では、甲社(非公開会社)がCから甲社株式(300株/1000株)を取得し、その対価として甲社が保有する丙社(非公開会社)の株式をCに譲渡する場合において、③甲社で会社法上必要となる手続と④乙社で会社法上必要となる手続が問われています。
③では、㋘自己株式を「特定の株主」との「合意により・・有償で取得する」場合における株主総会特別決議と売主追加請求通知、及び㋙重要な子会社の株式を譲渡する場合における株主総会特別決議と事前通知が必要です。
㋘ Aランク(条文知識の掲載あり)
㋙ Aランク(事業譲渡の章で条文知識の掲載あり)
④では、㋚一人会社における譲渡制限株式の譲渡についての会社承認の要否が問題となります。
㋚ Aランク(論証あり)
.
民事訴訟法
設問1では、XがYを被告として自動車衝突事故についての債務の不存在確認訴訟を提起したところ、YがXを被告として同一債務の一部についての明示的一部請求の給付訴訟を反訴として提起したという事案において、①本訴と反訴とが部分的に同じであること、②反訴が重複起訴禁止に抵触するか、及び③反訴要件(136条)の充足性について確認した上で、④給付訴訟が反訴として適法に提起されたことにより債務不存在確認訴訟の確認の利益が失われるかについて論じることが求められています。
①では、㋐旧訴訟物理論、㋑同一事故により生じた同一の身体傷害を理由とする財産的損害と精神的損害に係る損害賠償請求権の訴訟物としての一個性、㋒一部請求の肯否、及び㋓給付訴訟と債務不存在確認訴訟における訴訟物の同一性に関する知識を使うことになります。
㋐ Bランク(論証あり)
㋑ Bランク(論証あり)
㋒ Aランク(論証あり)
㋓ Aランク(論証の理由付けとして掲載あり)
②では、㋔「事件」の同一性の判断枠組み、㋕反訴と重複起訴禁止の関係についての知識を使うことになります。
㋔ Aランク(総まくり論証集には[論点]以外の論文知識も反映されている)
㋕ Aランク(本問の同種事案を前提とした説明まで掲載あり)
③では、㋖136条に関する条文知識を使うことになります。
㋖ Bランク(総まくり論証集には[論点]以外の論文知識も反映されている)
④では、給付訴訟が反訴として適法に提起されたことにより債務不存在確認訴訟の確認の利益が失われるのではないかについて、㋗給付訴訟が反訴として適法に提起されたことにより債務不存在確認訴訟の確認の利益が失われるとした最高裁平成16年判決に関する知識を使い、反訴が明示的一部請求であるという特殊性を踏まえながら論じることになります。
㋗ Aランク(Aランク分野である重複起訴禁止の脚注で、判例の結論及び根拠の掲載あり)
設問2では、本訴(債務不存在確認訴訟)の請求認容判決と反訴(一部請求)の請求棄却判決の確定後にYがこれらの前訴判決の確定後に生じた各症状による損害の賠償を求めて給付訴訟を提起した事案において、Yの残部請求が認められるための根拠について判例の立場に言及しながら説明することが求められており、⑤反訴に対する請求棄却判決との関係では明示的一部請求に対する棄却判決確定後における残部請求に関する最高裁平成10年判決の射程、⑥本訴に対する認容判決との関係では前訴判決後に顕在化した後遺症による損害について前訴で請求しない旨の明示があったと擬制した最高裁昭和42年判決の射程が問題となります。
⑤ Aランク(論証あり)
⑥ Aランク(論証あり、判例とは異なる2つの理論構成も掲載あり)
.
刑法
第1に、甲がBに対して自己がX組組員であることを秘すとともに、本件居室の使用目的について人材派遣業の事務所としての使用する予定であると嘘を告げた上で、不動産賃貸借契約書に署名・捺印し、Bとの間で本件居室を目的物とする賃貸借契約を締結したことについて、居住の利益を客体とする2詐欺既遂罪の成否が問題となり、ここでは①挙動による欺罔及び②欺罔行為の対象の重要事項性が主たる論点となります。
① Bランク(暴力団関係者であることを告げずにゴルフ場の施設利用の申込みをした事案に関する最高裁平成26年決定の掲載あり)
② Bランク(上記事案で重要事項性まで問題にした場合における当てはめのポイントの掲載あり)
第2に、甲が不動産賃貸借契約書に変更前の氏名を記入した上でその認印を押し、これをBに渡したことについて、有印私文書偽装罪及び同行使罪の成否が問題となり、有印私文書偽装罪の成否においては、③甲が変更後の氏名ではなく変更前の氏名を用いたことが「偽造」に当たるのかについて、通称・偽名の使用に関する判例の立場を踏まえて論じることになります。
③ Bランク(論証あり)
第3に、甲が丙からスタンガンで攻撃されると誤信して身を守るために拳で丙の顔面を1回殴り、丙を死亡させたことについて、まず初めに傷害致死罪の成否が問題となり、ここでは、誤想防衛の成否が主たる論点となります。誤想防衛の成立を理由として傷害致死罪の成立を否定した場合には、過失致死罪又は重過失致死罪の成否まで検討することになります。
傷害致死罪の成否では、④誤想防衛に関する一般論を論じた上で、甲の認識を前提として正当防衛の成立要件の充足性を検討することになり、その過程で、⑤予期された侵害の「急迫」性、⑥「やむを得ずにした行為」の意味(結果としての相当性VS行為としての相当性)及び当てはめが主たる検討事項になると思われます。
④ Bランク(論証あり)
⑤ Aランク(最高裁平成29年決定を踏まえた論証あり)
⑥ Aランク(論証あり)
過失致死罪又は重過失致死罪の成否では、⑦誤想防衛の場面における「過失」の意味を踏まえて論じることになります。
⑦ Bランク(誤想防衛の一般論に関する論証集の[補足]として掲載あり)
第4に、甲が自らの暴行により丙が身動きをしなくなり、意識を失っていることを認識しながら、丙に対する怒りから、丙の腹部を足で3回蹴ることにより丙に加療約1週間を要する腹部打撲の傷害を負わせたことについて、傷害罪の成否が問題となり、ここでも、⑧甲の認識を前提として正当防衛の成立要件の充足性を検討することになります。なお、誤想防衛の事案において⑨過剰防衛の一体性に関する議論を展開することまで求められているのかは定かでありません。
⑧ Bランク(論証あり)
⑨ Aランク(論証あり)
.
刑事訴訟法
常習傷害罪の事案における一事不再理効の客観的範囲として、①一事不再理効の定義、②一事不再理効の客観的範囲に関する原則論(公訴事実の同一性)及び③一事不再理効の客観的範囲の例外(同時処理可能性の有無による例外の肯否)が問われています。
②では、㋐一事不再理効の客観的範囲が原則として「公訴事実の同一性」の範囲内であることとその根拠、㋑公訴事実の単一性と狭義の同一性の発動場面の違い、㋒常習犯事案における公訴事実の単一性の判断方法、及び㋓常習窃盗の事案に関する2つの最高裁判例の違いが問われています。
① Aランク
② ㋐ Aランク(論証あり)
㋑ Aランク(訴因変更の可否のところで説明あり)
㋒ Aランク(論証あり)
㋓ Aランク(常習窃盗の事案に関する判例を踏まえた答案例あり)
③ Aランク(論証あり)
.
以上の通り、令和2年予備試験論文と総まくり論証集は、全科目において、ほぼ100%対応しているといえます。
司法試験受験生の方だけでなく、予備試験受験生の方にも、秒速・総まくり2021及び総まくり論証集を使い、試験対策として確実なインプットを完成させて頂きたいと思います。
令和2年予備試験論文の参考答案・解説
令和2年司法試験論文の参考答案・雑感
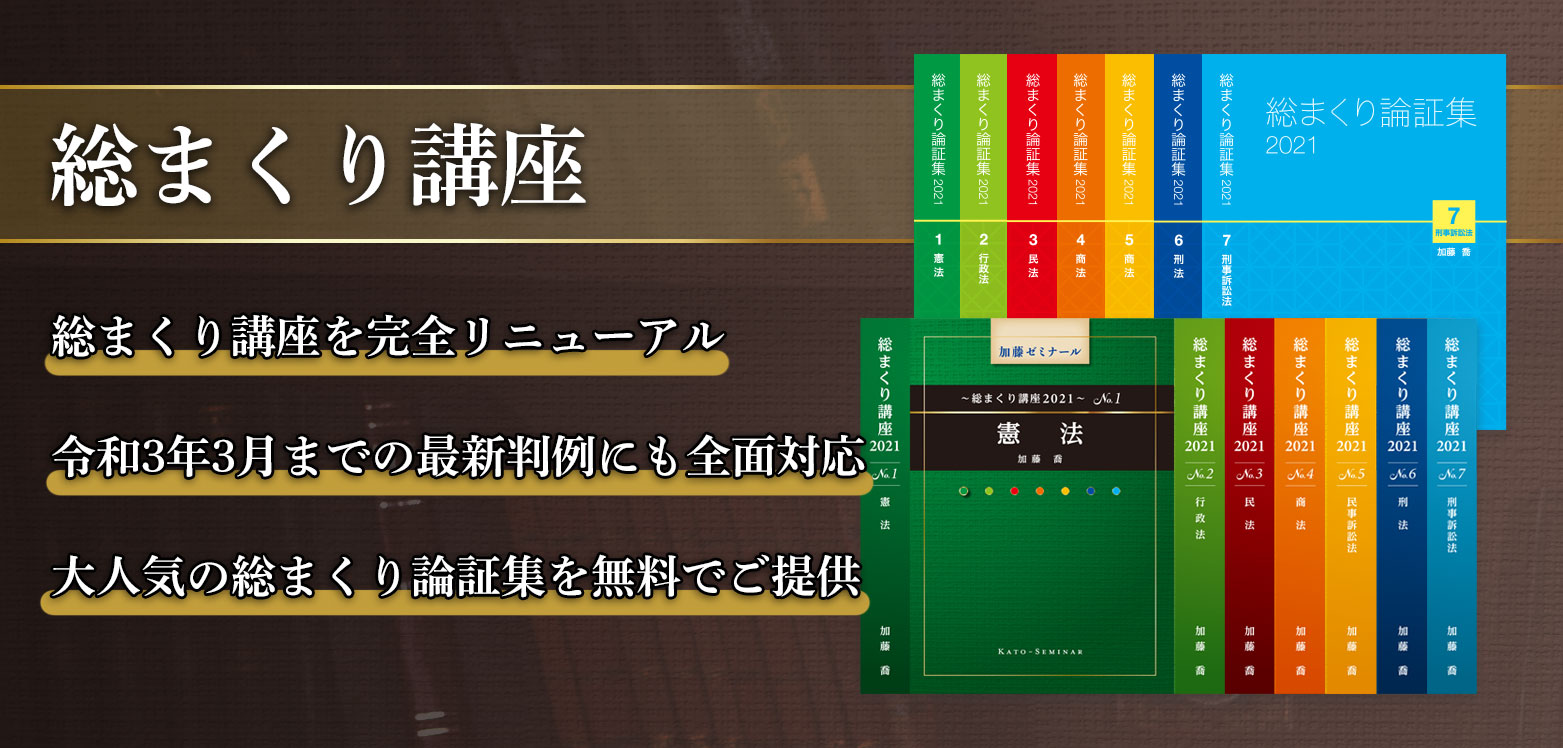
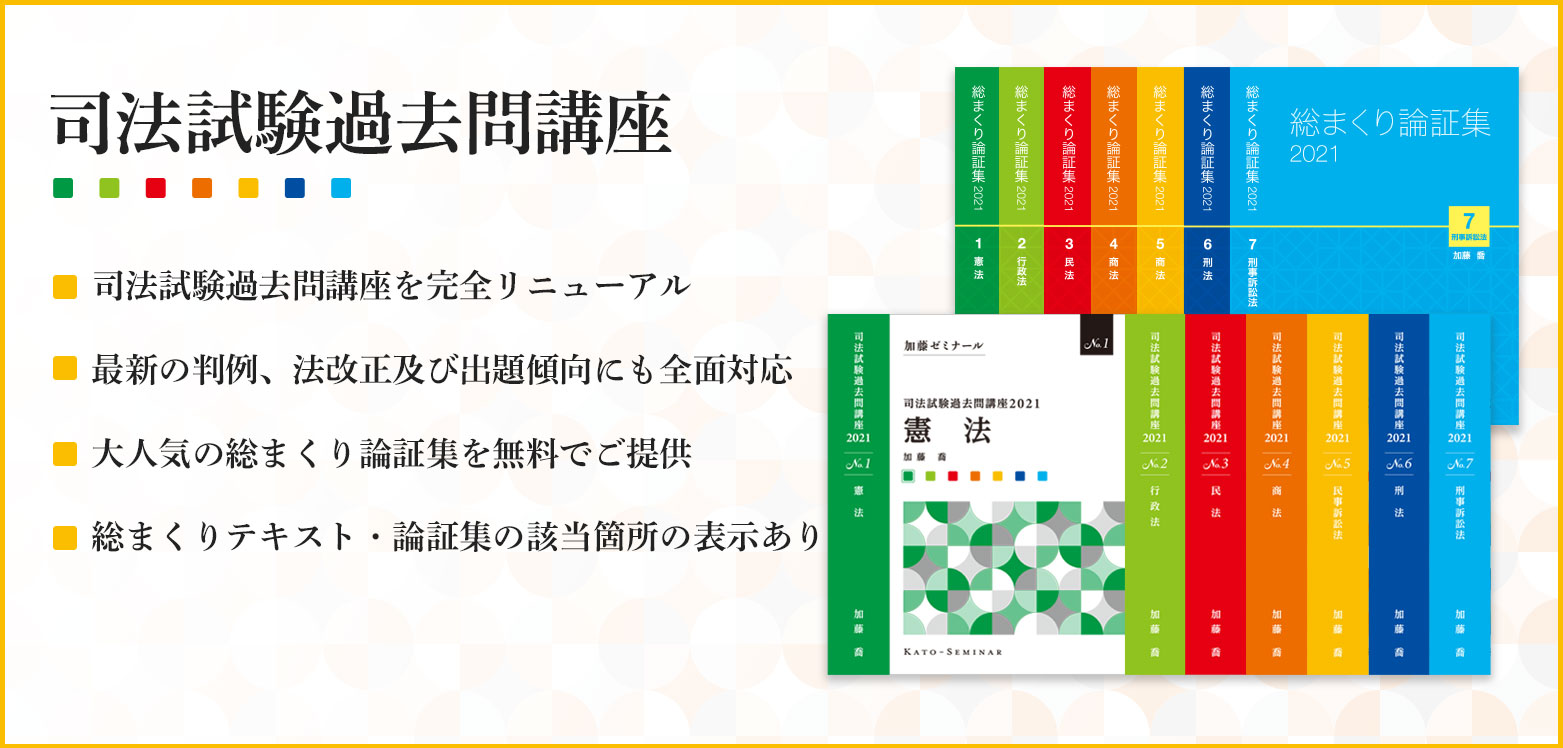
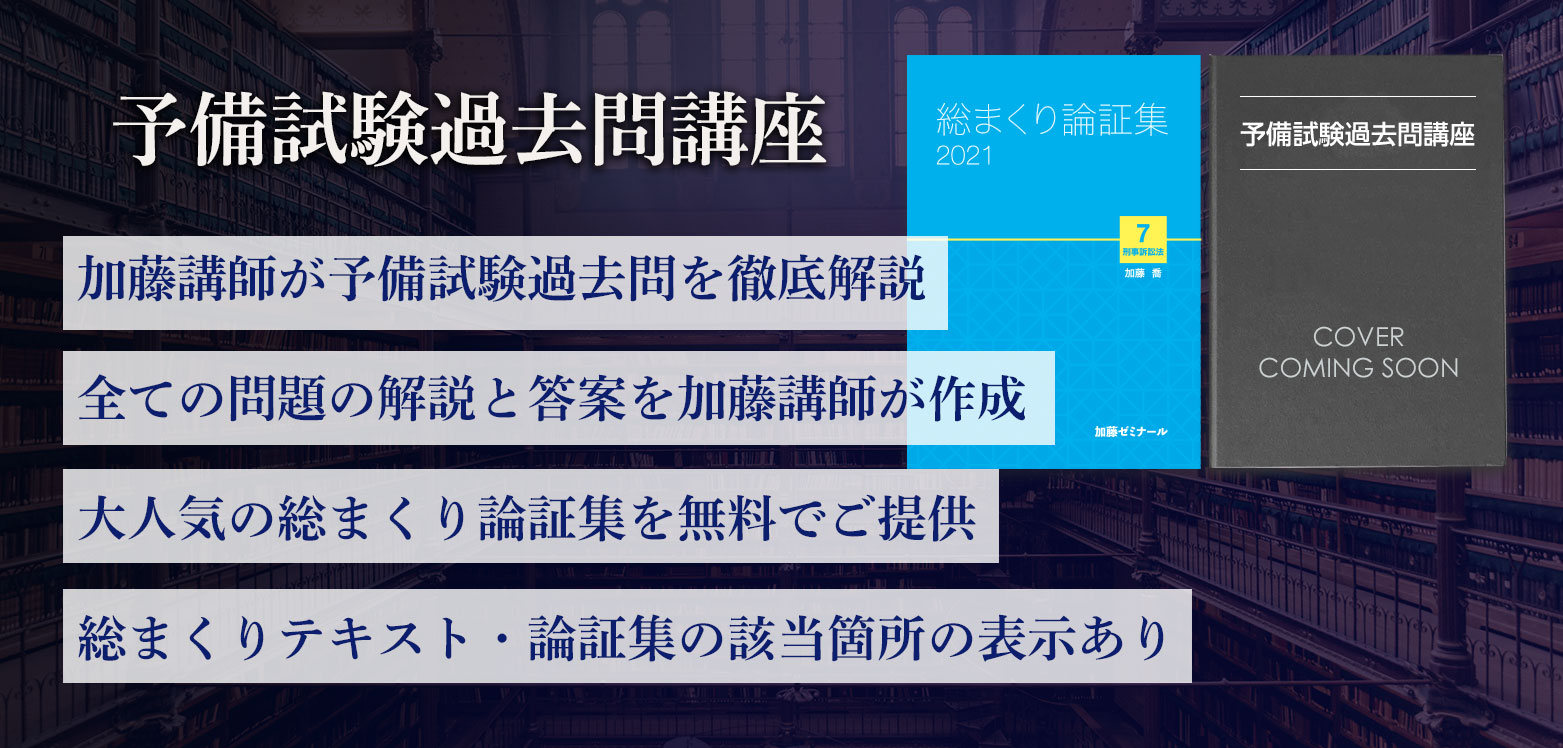
講義のご紹介
2025年度版の司法試験・予備試験対策講座一覧

2025年度版の司法試験・予備試験講座です!
2026年・2027年合格目標の方は、最新版の2025年度版をお買い求めください。
✅全動画配信中
✅全教材一括配送
✅最新の試験傾向に対応
✅講師作成の完全オリジナルテキスト

加藤ゼミナールでは、法曹を目指す方を対象として無料受講相談を実施しています。
・学歴や年齢は関係あるのか?
・どのプランが一番良いのか?
・他の予備校との違いは何か?
なんでもご相談ください!
経験豊富なスタッフがあなたの疑問や不安を解消いたします。
加藤ゼミナールのテキストのこだわり

加藤ゼミナールでは、受験生スタッフや合格者スタッフがテキストを作成するのではなく、全てのテキストを代表である加藤喬講師をはじめとする所属講師がいちから作成しています。
基本7科目の論文対策講座・労働法講座・法律実務基礎科目講座のテキストは全て、代表である加藤喬講師だけで作成しており、だからこそ、テキストは試験傾向にもしっかりと対応している、テキストどうしの一貫性が確保されているなど、クオリティが非常に高いです。
もっと見る

※スパムコメントを防ぐため、コメントの掲載には管理者の承認が行われます。
※記事が削除された場合も、投稿したコメントは削除されます。ご了承ください。