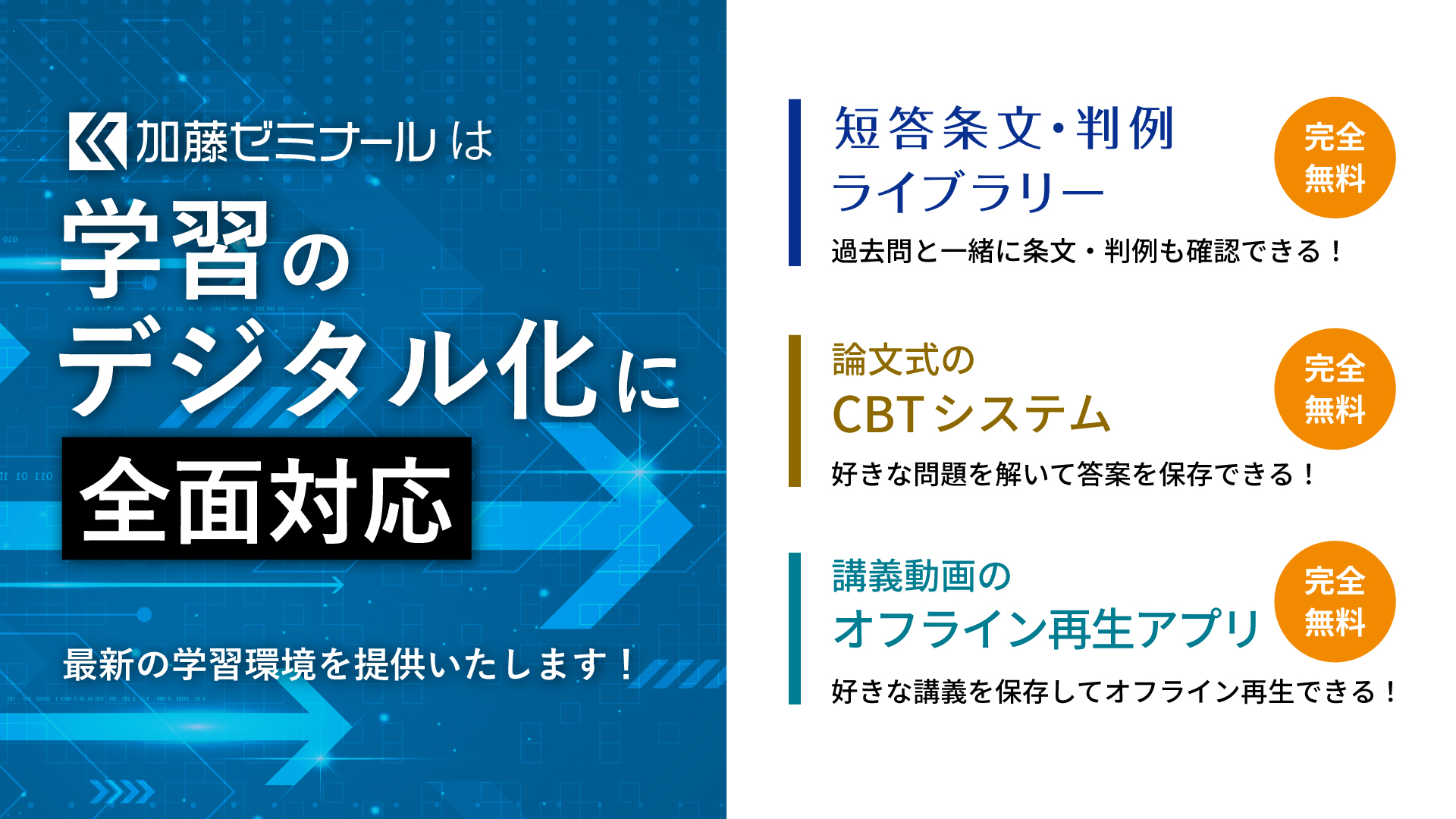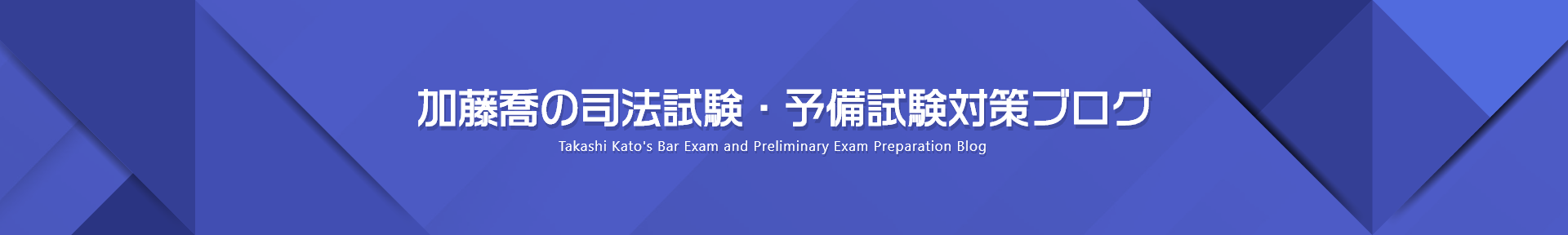商法と同様、かなり難しかったです。
設問1と2は、いずれも元ネタになっている最高裁判例がある上、設問1は平成30年司法試験設問1を少し捻った問題であるため、問題の所在及び参考にする判例については、比較的容易に気が付くことができました。
解説動画
解説レジュメ(問題文・解説・参考答案)を使い、問題文の読み方、現場での頭の使い方、科目ごとの答案の書き方、コンパクトなまとめ方、出題の角度といった問題の違いを跨いで役立つ汎用性の高いことについても丁寧に解説しています。
設問1
1.問題の所在
設問1では、債務不存在確認訴訟の係属中に同一債権について明示的一部請求訴訟が反訴として提起された場合において、「本訴についてどのような判決を下すべきか」と「本訴についての判決の既判力」の客観的範囲が問われています。
メインは、「本訴についてどのような判決を下すべきか」という論点であり、「債務不存在確認訴訟の係属中に同一債権の全体を訴訟物とする給付訴訟が提起された場合」において債務不存在確認訴訟が確認の利益を失うに至り却下されるとした最高裁平成16年判決(最一小判平成16・3・25・百29)の射程等を意識しながら論じることになります。
サブである「本訴についての判決の既判力」の客観的範囲については、「本訴についてどのような判決を下すべきか」が決まれば、自動的に結論が導かれます(但し、一部却下をみとる場合には、訴訟判決についての既判力という論点が生じます)。
2.本訴と反訴の訴訟物から確認する
「債務不存在確認訴訟の係属中に同一債権について明示的一部請求訴訟が反訴として提起された場合」における債務不存在確認訴訟の取扱いという論点は、同一債権について明示的一部請求訴訟が反訴として適法に提起された場合に顕在化するものです。仮に反訴が不適法なものであれば、反訴が却下されることになるため、反訴が提起されたことは本訴である債務不存在確認訴訟を維持する上での障害にはなり得ないからです。
そこで、上記論点に入る前提として、Yによる一部請求訴訟が反訴として適法に提起されているのかについて確認することになります。ここでは、重複起訴禁止(民事訴訟法142条)及び反訴要件(民事訴訟法136条)を検討することになります。いずれについても、本訴と反訴の訴訟物どうしを比較して判断することになります。したがって、まず初めに、本訴と反訴の訴訟物を明らかにすることになります。
本訴と反訴の訴訟物を明らかにする際には、軽くでいいので、旧訴訟物理論に立つことを明示するべきです。本問では、旧訴訟物理論と新訴訟物理論の対立は顕在化しませんが、本問と同じく両説の対立が顕在化しない事案に属する平成30年司法試験設問1の出題趣旨では、「訴訟物の捉え方については、複数の考え方があり得るところであり、どの立場に立つかによって評価に差がつくわけではないが、いずれにせよ、Bの訴えの訴訟物は、設問1を考える上で当然に明示する必要がある。」とあります。訴訟物理論について言及するようにと明示的に指摘されているわけではありませんが、上記の書きぶりからすると、訴訟物理論を明示することが求められているように読めます。
大部分の受験者が旧訴訟物理論に立って答案を書くと思われるため、以下では、旧訴訟物理論を前提として解説いたします。
XがXのYに対する本件事故による損害賠償債務が一切存在しないと主張して本訴を提起していることから、本訴の訴訟物は、本件事故による損害賠償請求権(民法709条)が一切存在しないことであると考えられます。具体的には、①物損に関する損害賠償請求権、②Yが反訴で主張している「治療費用・・の支出と通院に伴う慰謝料の一部」を損害とする損害賠償請求権、及び③①②以外の本件事故に関する損害賠償請求権が存在しないことです(但し、厳密には、設問2で前訴判決後に顕在化した各症状を原因とする損害の賠償請求権の不存在については確認対象から除外する旨の明示があったと擬制する構成を採用した場合には、本訴の訴訟物は、全損害から上記損害を除いたものに関する損害賠償請求権の不存在となります)。
①②③は、全て1個の損害賠償請求権として1個の訴訟物を構成します。最高裁昭和48年判決(最一小判昭和48・4・5・百74)では、「同一事故により生じた同一の身体傷害を理由とする財産上の損害と精神上の損害とは、原因事実および被侵害利益を共通にするものであるから、その賠償の請求権は一個であり、その両者の賠償を訴訟上あわせて請求する場合にも、訴訟物は一個であると解すべきである。」と判示しているからです。①②③の分類は、設問1・2におけるYの主張と設問1における裁判所の心証を反映したものです。「Yは、本件事故による物損について損害額の全額の支払いを受けている」から物損はないとの心証は①、「Yは、・・本件事故により頭痛の症状が生じ、・・本件事故による治療費用としてYが多額の支出をしているので、その支出と通院に伴う慰謝料の一部のみをまずは請求すると主張」しているとの部分が②、「その他、本件事故によるYの人的損害の発生を認めるに足りる証拠はない」との裁判所の心証及びYが「前訴判決後に生じた各症状」による財産的損害及び精神的損害を残部として請求したとの部分が③に対応します。設問1及び2で答案を書きやすくするために、便宜上、①②③の3つに分類した上で、ナンバリングをしています。
反訴は一部請求です。一部請求否定説に立つのであれば、反訴の訴訟物が①ないし③となるのに対し、一部請求肯定説に立つのであれば、反訴の訴訟物は明示された②に限定されます。このように、一部請求に関する学説対立が反訴の訴訟物の捉え方に影響を及ぼすため、一部請求に関する学説対立が顕在化することになります。判例は、一部であることの明示があれば訴訟物が明示された一部に限定されるとする立場です。この見解からは、反訴の訴訟物は明示された②の存在だけとなります。
そして、債務不存在確認訴訟は給付訴訟の反対形相であり、両者の訴訟物は同一であると解されているため、本訴と反訴では、②の限度で訴訟物が同じであることになります。
3.反訴の適法性
本訴と反訴とが②の限度で訴訟物を同じくしていることを前提として、反訴について、重複起訴禁止(民事訴訟法142条)及び反訴要件(民事訴訟法136条)を検討することになります。いずれについても、本訴と反訴の訴訟物どうしを比較して判断することになります。
重複起訴が禁止される「事件」の同一性は、当事者と審判対象の同一性から判断されます。重複起訴禁止の主たる趣旨が既判力の矛盾抵触の防止にあることから、当事者の同一性は、当事者の同一性は、民事訴訟法115条1項1号ないし4号により既判力が及ぶ者どうしの間にも認められます。また、既判力が訴訟物の存否に対する判断に生じるのが原則である(民事訴訟法114条1項)ことから、審判対象の同一性は訴訟物が同一である場合に認められます。
本訴と反訴とでは、原告と被告が入れ替わっているだけであり、XとYは、訴訟で対立した「当事者」(民事訴訟法115条1項1号)として、既判力が及ぶ関係に立つ者どうしであるといえます。したがって、当事者の同一性が認められます。また、本訴と反訴とは、②の限度で訴訟物を同じくしているため、②の限度で審判対象の同一性が認められます。したがって、反訴は、本訴と同一の「事件」について提起されたものであるといえます。
もっとも、本訴と反訴の訴訟物が同一である場合、両請求の関連性の強さから裁判所が弁論を分離する権限(民事訴訟法152条1項)が制限されるため、後に弁論が分離され別々に審理・判断されることで重複起訴禁止の弊害が生じるという事態は起こり得ません。したがって、反訴は、「更に訴えを提起すること」に当たらず、重複起訴禁止(民事訴訟法142条)に抵触しません(なお、反訴だからといって当然に重複起訴禁止に抵触しないわけではないことについては、こちらの重要判例解説の記事でご確認ください)。
反訴は、本訴と②の訴訟物を同じくするため「本訴の目的である請求・・と関連する」(民事訴訟法146条1項本文)ともいえます。また、反訴が本訴の「口頭弁論の終結に至るまで」に、「本訴の係属する裁判所」に提起されていますし(民事訴訟法146条1項本文)、争点である損害賠償請求権の発生の有無・範囲については本訴の審理が反訴の審理を包摂することになるため「著しく訴訟手続を遅延させる」(同条項但書2号)ともいえません。したがって、反訴は、反訴要件も満たすため、適法に提起されたといえます。
4.反訴の適法な提起により、本訴が確認の利益を失うに至り、却下されることになるか。
前掲最高裁平成16年判決は、「債務不存在確認訴訟の係属中に同一債権の全体を訴訟物とする給付訴訟が提起された場合」について、債務不存在確認訴訟は確認の利益を失い却下されると解しています。その理由については、給付請求権の存在を確定する既判力(民事訴訟法114条1項)に加えて執行力(民事執行法22条1号)も認められる給付訴訟の判決効が債務不存在確認訴訟の判決効を包含するからであると説明されています(「民事訴訟法判例百選」第5版事件29解説)。
しかし、本件における反訴と本訴とでは、訴訟物が②の限度でしか重なっていませんから、本訴には、①・③の存否も既判力により確定できるという、反訴にはない独自の意味があります。そのため、反訴の判決効が本訴の判決効を包含するとはいえません。したがって、最高裁平成16年判決の射程は、少なくとも、本件についてそのままの形で全面的に及ぶわけではありません。
その上で考えられる法律構成は、2つです。
1つ目が、本訴(債務不存在確認訴訟)を②の限度で却下するとの構成です。2つ目が、本訴(債務不存在確認訴訟)を全面的に維持する(②の限度でも却下しない)との構成です。
最高裁平成16年判決の射程を否定した際に用いた「本訴には、①・③の存否も既判力により確定できるという、反訴には独自の意義がある」との理由付けとの相性が良いのは、1つ目の構成です。ただ、試験現場で「訴訟物の一部についての却下」という意味での一部却下を認めることができるのか?という疑問を抱く方は少なくないと思いますし、仮に1つ目の構成によるのであれば、「訴訟物の一部についての却下」という意味での一部却下を認めることができるのかについて、別途、論じる必要があります。私の答案では、そこまで言及する紙面の余裕がないため、2つ目の構成に立っています。
最高裁平成16年判決の根拠が本件には(部分的に)妥当しないとして本判決の射程を否定することができれば、合格水準ですから、どちらの構成でも構いません。「訴訟物の一部についての却下」という意味での一部却下の肯否についてまで言及することは、上位答案(1桁~2桁前案)の水準です。ここで書きすぎた結果、設問2で十分な論述をすることができなくなるのでは、本末転倒ですし。
5.2つ目の構成を前提とした判決と、その判決について既判力の客観的範囲
2つ目の構成を前提とする場合、裁判所は、①②③すべてに対して本案判決をすることになります。設問1に書かれている裁判所の心証に従うと、全部認容判決を下すことになります。
この全部認容判決について生じる既判力の客観的範囲は、①②③の不存在すべてに及びます。つまり、①②③の不存在について既判力が生じることになります(民事訴訟法114条1項)。
ちなみに、1つ目の構成を前提にすると、①③に対しては認容判決を下し、②に対しては却下判決を下すことになります。そして、①③の不存在について既判力が生じることを指摘するとともに、却下判決については既判力が生じるのか(訴訟判決にも既判力が生じるのか)、仮に生じるとしてどういった形で既判力が生じるのか(訴訟要件全般の不存在について既判力が生じるのか)についても軽く言及することになると思われます。
設問2
1.論述の方向性
司法試験でも予備試験でも、設問等により、論述の方向性が指示されることがあります。
設問2では、「後訴においてYの残部請求が認められるためにはどのような根拠付けが可能かについて、・・Y側の立場から論じなさい」とあるため、残部請求が認められるとの結論を導く理論構成を示す必要があります。
2.反訴に対する判決との関係
まずは、既判力の作用から考えます。信義則について検討するのは、その後です。例えば、平成29年司法試験設問3の出題趣旨では、売買代金支払請求(前訴)に対する代金額を200万円とする引換給付判決が下され、それが確定した後に、売主が買主に対して代金200万円の支払い給付訴訟を提起した事案について、「本問では、既判力などの制度的効力を否定する場合には、既判力以外の理由、例えば信義則などにより、Xが本件絵画の売買契約の成否及びその代金額を後訴で争えなくなるか否かについて検討することも求められる。」とあります。
114条1項の既判力は、これが生じる前訴訴訟物が後訴訴訟物と同一、先決、又は矛盾の関係に立つ場合に後訴に作用します。反訴の訴訟物は②だけですから、反訴に対する判決(以下「反訴判決」とします)の既判力は②の不存在についてのみ生じます。そうすると、②に属しない「前訴判決後に生じた各症状」に関する損害賠償請求権を訴訟物とする後訴と反訴とでは訴訟物が異なるため、同一関係は認められません。先決・矛盾関係にもありませんから、反訴判決の既判力は後訴に作用しません。したがって、Yが後訴で前訴基準時前の事由たる各症状の発生を主張することは、反訴判決の既判力によっては妨げられません。
次に、信義則について考えます。最高裁平成10年判決(最二小判平成10・6・12・百80)は、金銭債権の数量的一部請求に対する棄却判決確定後の残部請求について、「このような請求の当否を判断するためには、おのずから債権の全部について審理判断することが必要になる。・・数量的一部請求を全部又は一部棄却する旨の判決は、このように債権の全部について行われた審理の結果に基づいて、・・後に残部として請求し得る部分が存在しないとの判断を示すものにほかならない。したがって、右判決が確定した後に原告が残部請求の訴えを提起することは、実質的には前訴で認められなかった請求及び主張を蒸し返すものであり、前訴の確定判決によって当該債権の全部について紛争が解決されたとの被告の合理的期待に反し、被告に二重の応訴の負担を強いるものというべきである」から、「特段の事情がない限り、信義則に反して許されないと解するのが相当である。」と判示しています。
本問では、例外的に残部請求が信義則に反しないとされる「特段の事情」を肯定する必要があります。本判決が「数量的一部請求を・・棄却する旨の判決・・が確定した後に原告が残部請求の訴えを提起することは、・・信義則に反して許されない」との原則ルールを導いた理由からすると、原則ルールに対する例外である「特段の事情」が認められるのは、㋐残部の不存在についてまでは前訴棄却判決により示されておらず(つまり、前訴棄却判決が「後に残部として請求し得る部分が存在しないとの判断を示すもの」であるとはいえない)、かつ、㋑前訴被告においても後訴で残部が請求されることを予測していた又は容易に予測することができたため「確定判決によって当該債権の全部について紛争が解決されたとの被告の合理的期待」が生じていたとはいえないときであると思われます。
前訴段階で顕在化していたとされる②に関する傷害と、残部請求に係る前訴判決の確定後に生じた各症状とは、異なる種類の傷害である上、後者が前訴判決後に生じたという意味で顕在化時点も大きく異なります。特に、残部請求に係る前訴判決の確定後に生じたものである(すなわち、前訴基準時には未顕現であった)ことが重要です。そして、本判決は、「数量的一部請求を全部又は一部棄却する旨の判決は、このように債権の全部について行われた審理の結果に基づいて、・・後に残部として請求し得る部分が存在しないとの判断を示すものにほかならない。」とする理由として、「裁判所は、当該債権の全部について当事者の主張する発生、消滅の原因事実の存否を判断し」た上で発生が認められた債権全額を対象として消滅原因事実による控除の要否・範囲を判断するとの過程を経るということを挙げています。ところが、前訴裁判所は、前訴基準時までに顕在化している原因事実に基づく損害の存否については審理判断しているが、前訴基準後に顕在化した原因事実に基づく損害の存否についてまでは審理判断することができていないため、そのような審理判断を経て下された請求棄却判決によって前訴基準後に顕在化した原因事実に基づく損害が存在しないことまで示されているとはいえません。したがって、㋐を満たします。
Xが前訴の段階から本件事故によるYの人的損害の発生についてXY間の主張が食い違っていることを認識していたことと、自動車交通事故により一定期間経過後に後遺症が顕在化することは決して珍しいことでないことから、Xとしては、前訴判決後に後遺症が顕在化した場合には別途それについての残部請求がなされることについて、前訴判決前から容易に予測することができたといえます。したがって、㋑も満たします。
よって、「特段の事情」が肯定されるため、Yの残部請求は、反訴判決との関係では、信義則違反として却下されることもありません。
3.本訴に対する判決との関係
本訴に対する判決(以下「本訴判決」とする)の既判力により、③の不存在の一つとして、本件債権の不存在も確定されるのが原則です。そうすると、本訴判決の既判力は、本件債権を訴訟物とする後訴について同一関係を根拠として作用することになり、後訴において本訴基準時前の事由たる各症状の発生を主張することは許されないのが原則です。
例外として、後訴(残部請求)においてYが前訴判決後に顕在化した各症状を原因とする損害の発生を主張することが本訴判決の既判力により遮断されないとするための理論構成は、3つあります。
1つ目は、最高裁昭和42年判決(最三小判昭和42・7・18・百82)のように、一部請求理論を前提として、前訴では前訴基準時までに顕在化していない後遺症を原因とする損害の賠償請求権を訴訟物から除外する旨の明示があったと擬制するものです。これによると、債務不存在確認訴訟の訴訟物から「前訴判決後に顕在化した各症状を原因とする損害の賠償請求権」が除外されることになるため、本訴判決の既判力は、実は、「前訴判決後に顕在化した各症状を原因とする損害の賠償請求権」以外の不存在についてしか生じていないということになります。その結果、本訴判決の既判力が生じている本訴の訴訟物と後訴の訴訟物とは同一関係に立たないことになります。先決・矛盾関係にもありませんから、本訴判決の既判力は残部請求に作用しないことになります。
もっとも、本判決は、給付訴訟において、前訴基準時には顕在化していない後遺症を原因とする損害の賠償請求はしない旨の明示があったと擬制したものですから、債務者側から提起されている債務不存在確認訴訟についてまで当然にその射程が及ぶわけではありません。したがって、仮に1つ目の理論構成による場合には、給付訴訟に関する判例理論の射程を債務不存在確認訴訟にまで拡大することの可否についてまで論じる必要があります。さらに、設問1後段の結論で「本訴に対する判例の既判力は、債権全部の不存在について生じる」と書いている場合には、設問2の理論構成と設問1後段の結論とが矛盾することになってしまいます。このことに配慮して、私の答案では、設問1後段の結論については「本訴については全部認容の判決を下すべきである。既判力は、①ないし③の不存在について生じる。」とする一方で、設問2では「したがって、本訴では本件債権を除く債権の不存在の確認を求める(③から本件債権を除外する)旨の明示があったと擬制されるから、本訴判決の既判力は後訴に作用しない。」とすることにより、設問間における矛盾を回避するための工夫をしています。
2つ目は、本訴と後訴とで訴訟物の同一であることを根拠として本訴判決の既判力が後訴に作用するという原則論を維持した上で、前訴判決後に顕在化した各症状を原因とする損害の発生を基準時後の事由に位置づける構成です。この理論構成による場合には、未顕現の後遺症も含め不法行為時に全損害が発生していると解されているにもかかわらず、どうして後遺症に基づく損害の発生を基準時後の事由に位置づけることができるのかについて説明する必要があります。
3つ目は、本訴と後訴とで訴訟物の同一であることを根拠として本訴判決の既判力が後訴に作用するという原則論を維持し、前訴判決後に顕在化した各症状を原因とする損害の発生を基準時前の事由に位置づけた上で、前訴において各症状を原因とする損害の発生を主張することについて期待可能性がなかったとして既判力による遮断を例外的に否定するというものです。この理論構成による場合には、基準時前の事由の主張が例外的に許容される余地があることについて、既判力の根拠論に遡って説明する必要があります。
参考答案
設問1
1.まず、本訴と反訴の訴訟物から確認する
手続保障及び審判対象の明確化のため、訴訟物は実体法上の請求権ごとに分断して捉えるべきと解する。そして、XがXのYに対する本件事故による損害賠償債務が一切存在しないと主張して本訴を提起していることから、本訴の訴訟物は、本件事故による損害賠償請求権(民法709条)が一切存在しないことである。具体的には、①物損に関する損害賠償請求権、②Yが反訴で主張している「治療費用…の支出と通院に伴う慰謝料の一部」を損害とする損害賠償請求権、及び③①②以外の本件事故に関する損害賠償請求権が存在しないことである。
反訴は一部請求である。実体法上は債権の分割行使が債権者の自由とされているため実体法上の権利の実現過程である民事訴訟でも一部請求を認める必要がある一方で、明示がない場合における残債務がないという被告の合理的期待に配慮する必要もある。そこで、一部であることの明示があれば、訴訟物は債権の一部に限定され、確定判決の既判力も債権の一部についてのみ生じると解する。これが判例の立場である。Yが②だけを請求すると明示して反訴を提起しているため、反訴の訴訟物は②の存在である。
債務不存在確認訴訟は給付訴訟の反対形相であり、両者の訴訟物は同一であると解されているから、本訴と反訴では、②の限度で訴訟物が同じであることになる。
2.次に、反訴の適法性を確認する。
反訴は本訴と当事者及び②の訴訟物を同じくするため、同一「事件」について提起されたものである。もっとも、本訴と反訴の訴訟物が同一である場合、両請求の関連性の強さから裁判所が弁論を分離する権限(152条1項)が制限されるから、後に弁論が分離され別々に審理・判断されることで重複起訴禁止の弊害が生じるということはない。したがって、反訴は、「更に訴えを提起すること」に当たらず、重複起訴禁止(142条)に抵触しない。
反訴は、本訴と②の訴訟物を同じくするため「本訴の目的である請求…と関連する」(146条1項本文)ともいえ、適法である。
3.そこで、適法な反訴提起により本訴が却下されるかが問題となる。
判例は、債務不存在確認訴訟の係属中に同一債権について給付訴訟が反訴として適法に提起された場合には、前者は確認の利益を失い却下されると解している。給付請求権の存在を確定する既判力(114条1項)に加えて執行力(民事執行法22条1号)も認められる後者の判決効が前者の判決効を包含するからである。しかし、本件反訴と本訴とでは訴訟物が②の限度でしか重なっていないから、本訴には①・③の存否も既判力により確定できるという反訴にはない独自の意味があるから、反訴の判決効が本訴の判決効を包含するとはいえない。したがって、判例の射程は及ばず、本訴は却下されない。
4.裁判所の心証に従うと、本訴については全部認容の判決を下すべきである。既判力は、①ないし③の不存在について生じる。
設問2
1.反訴に対する判決との関係
(1) 114条1項の既判力は、これが生じる前訴訴訟物が後訴訴訟物と同一、先決、又は矛盾の関係に立つ場合に後訴に作用する。反訴の訴訟物は②だけだから、反訴判決の既判力は②の不存在についてのみ生じる。そうすると、②に属しない「前訴判決後に生じた各症状」に関する損害賠償請求権(以下、本件債権とする)を訴訟物とする後訴と反訴とでは訴訟物が異なるから、同一関係にない。先決・矛盾関係にもないから、反訴判決の既判力は後訴に作用しない。したがって、Yが後訴で前訴基準時前の事由たる各症状の発生を主張することは、反訴判決の既判力によっては妨げられない。
(2) 判例は、金銭債権の数量的一部請求に対する棄却判決確定後の残部請求について、請求の当否の判断では債権全部についての審理判断を経るのが通常であるため、このような審理の結果に基づく請求棄却判決は後に請求し得る残部が存在しないとの判断を示すものにほかならないとの理由から、特段の事情のない限り、実質的な前訴の蒸し返しとして信義則に反し許されないと解している。
しかし、前訴段階で顕在化していたと主張されている②に関する傷害と、前訴判決後に生じた各症状とは、異なる種類の傷害である上、後者が前訴判決後に生じたという意味で顕在化時点も大きく異なる。そのため、②と本件債権とは実質的な発生事由を異にするといえるから、本件債権については実質的に前訴判決での審理・判断を経ていないといえる。したがって、特段の事情が認められるから、反訴判決との関係では後訴は遮断されない。
2.本訴に対する判決との関係
(1) 本訴判決の既判力により、③の不存在の一つとして、本件債権の不存在も確定されるのが原則である。そうすると、本訴判決の既判力は、本件債権を訴訟物とする後訴について同一関係を根拠として作用することになり、後訴において本訴基準時前の事由たる各症状の発生を主張することは許されないのが原則である。
(2) もっとも、判例には、被害者が事故による損害の賠償を求める給付訴訟を提起し、認容判決が確定した後に、前訴基準時後に後遺症が悪化したことによる損害の賠償を求める給付訴訟を提起した事案において、一部請求理論を前提として前訴では未顕現の後遺症に関する損害の賠償請求はしない旨の明示があったと擬制することで前訴と後訴の訴訟物の同一性を否定することにより、前訴判決の既判力が後訴に作用することを防ぎ、被害者の救済を図ったものがある。債務不存在確認訴訟でも一部請求が認められていること、被害者の救済の必要性、及び訴訟当事者間の公平を理由として、債務者側が提起する債務不存在確認請求訴訟にも上記判例の射程が及ぶと解すべきである。したがって、本訴では本件債権を除く債権の不存在の確認を求める(③から本件債権を除外する)旨の明示があったと擬制されるから、本訴判決の既判力は後訴に作用しない。よって、残部請求が認められる。以上
※1. 参考答案は、2時間くらいで、総まくり講座及び司法試験過去問講座の内容だけで書いたものです。
※2. 答案の分量は「1枚 22行、28~30文字」の書式設定で4枚目の最終行(88行目)までで、文字数だと2400~2500文字くらいです。
講義のご紹介
試験対策講座のパンフレットを無料配布中!

最新版の試験対策講座のパンフレットを無料配布しています。
①予備試験対策講座2026
②司法試験対策講座2026
③法科大学院入試対策講座2026
3つのパンフレットから自由にお選びいただけます(複数選択も可能)。
・紙媒体のパンフレットの無料郵送📮
・デジタルパンフレットの無料送信📩
いずれも承っております。
紙媒体のパンフレットは2~3営業日中に郵送し、デジタルパンフレットは即時にメール送信いたします。
加藤ゼミナールの試験対策講座にご興味のある方は、是非パンフレットをご覧ください!
学習のデジタル化に全面対応
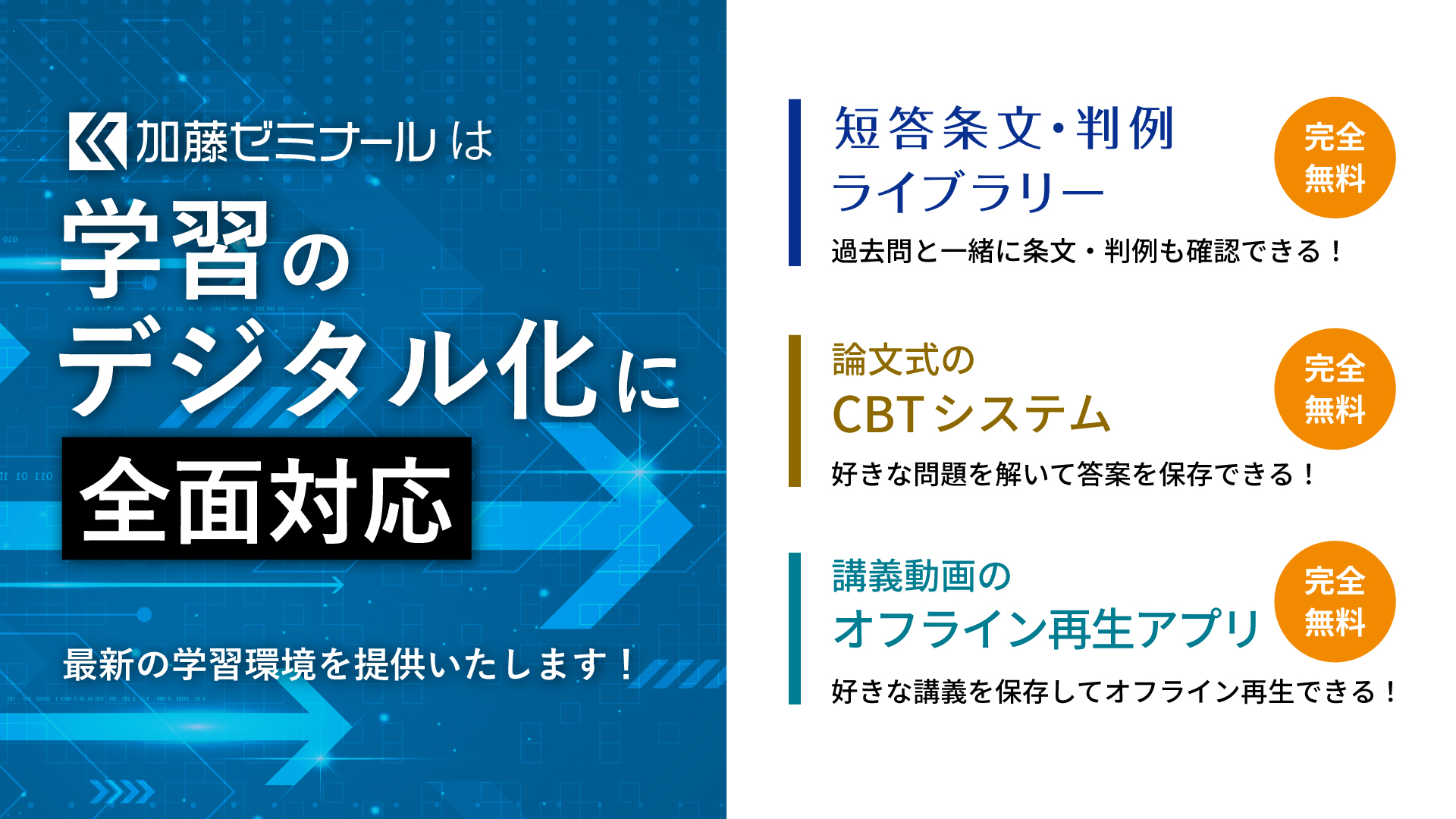
加藤ゼミナールは、①『短答条文・判例ライブラリー』、②『講義動画のオフライン再生アプリ』、③『論文式CBTシステム』をリリースいたしました。いずれのサービスも完全無料です。
①『短答・条文判例ライブラリー』は、短答過去問を条文・判例というコア知識に紐づけて整理したブラウザベースの学習ツールです。全年度分の過去問と出題実績のある条文・判例が集約されており、本サービスだけで短答対策を完成させることができます。
②『講義動画のオフライン再生アプリ』では、受講講座の動画の中から自由に動画を選んでスマートフォン等の端末にダウンロードすることにより、オンライン環境でいつでも・どこでも、講義動画を視聴することができます。
③『論文式CBTシステム』では、全年度分の司法試験過去問・予備試験過去問を自由に解くことができり、演習で使用した問題文と作成した答案をPDF形式で保存することができます。また、過去問以外の問題も自由にアップロードして解くことができます。

加藤ゼミナールでは、法曹を目指す方を対象として無料受講相談を実施しています。
・学歴や年齢は関係あるのか?
・どのプランが一番良いのか?
・他の予備校との違いは何か?
なんでもご相談ください!
経験豊富なスタッフがあなたの疑問や不安を解消いたします。
加藤ゼミナールのテキストのこだわり

加藤ゼミナールでは、受験生スタッフや合格者スタッフがテキストを作成するのではなく、全てのテキストを代表である加藤喬講師をはじめとする所属講師がいちから作成しています。
基本7科目の論文対策講座・労働法講座・法律実務基礎科目講座のテキストは全て、代表である加藤喬講師だけで作成しており、だからこそ、テキストは試験傾向にもしっかりと対応している、テキストどうしの一貫性が確保されているなど、クオリティが非常に高いです。
もっと見る

※スパムコメントを防ぐため、コメントの掲載には管理者の承認が行われます。
※記事が削除された場合も、投稿したコメントは削除されます。ご了承ください。