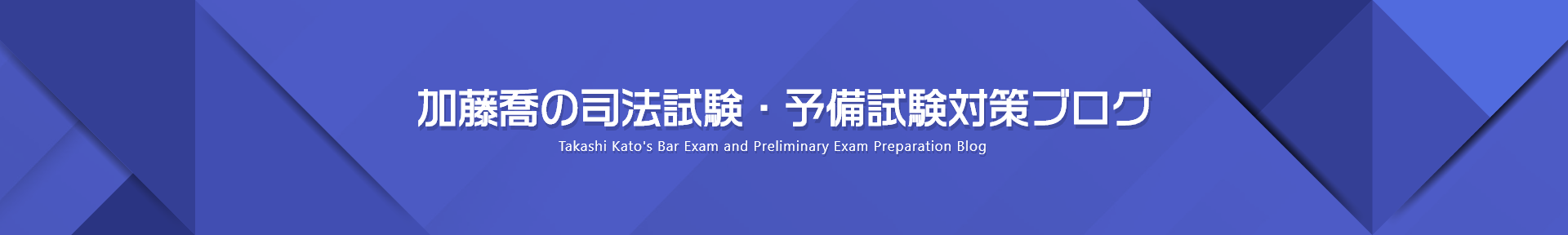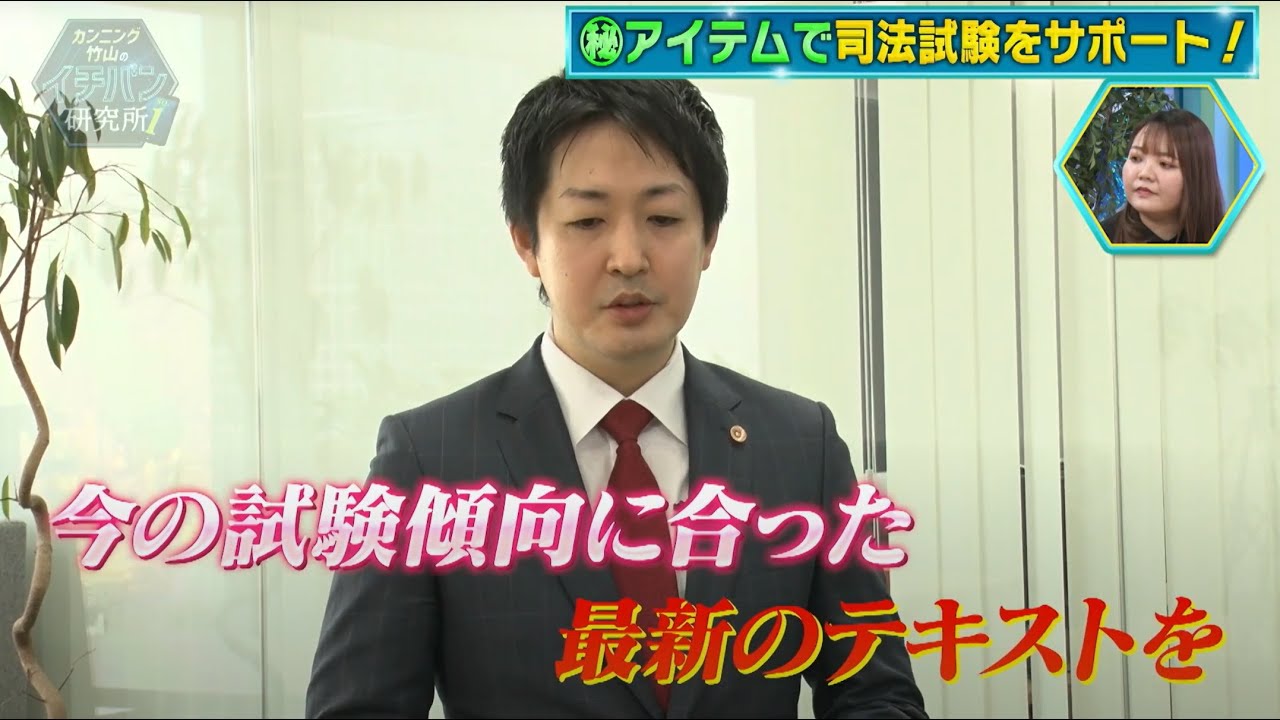司法試験・予備試験対策なら加藤ゼミナール!


加藤ゼミナールはもうすぐ開校4年目を迎えます。
開校当初から大変多くの方々にご利用いただき、令和5年司法試験では合格者数を212名まで伸ばすことができ、1位合格者や10位台合格者も輩出できました。
今期から中央ローを主席卒業した深澤直人氏が倒産法講座の担当講師として参画し、講師4名体制でこれまで以上に良質で幅広い講座を提供させていただきます。
加藤ゼミナールのテキストのこだわり


加藤ゼミナールでは、受験生スタッフや合格者スタッフがテキストを作成するのではなく、全てのテキストを代表である加藤喬講師をはじめとする所属講師がいちから作成しています。
基本7科目の論文対策講座・労働法講座・法律実務基礎科目講座のテキストは全て、代表である加藤喬講師だけで作成しており、だからこそ、テキストは試験傾向にもしっかりと対応している、テキストどうしの一貫性が確保されているなど、クオリティが非常に高いです。
加藤ゼミナールの講座を無料で体験受講して頂けます


加藤ゼミナールの販売講座の無料体験講座を公開しております。
加藤ゼミナールの司法試験・予備試験対策講座の受講を検討なさっている方は、是非ご覧下さいませ。
もっと見る